| 昭和42年8月 |
3つの研究所に分散していた国際漁業研究部門を統合。所長、庶務課、北洋資源部(函館)浮魚資源部、底魚海獣資源部、海洋部、東京分室、焼津分室及び漁業調査船俊鷹丸をもって業務を開始 |
| 昭和43年4月 |
企画連絡室を設置 |
|
| 昭和43年8月 |
東京分室を廃止 |
|
| 昭和44年4月 |
総務部、会計課を設置 |
|
| 昭和45年5月 |
北洋資源部を函館市より清水市へ移転 |
 |
| 昭和57年 4月 |
企画連絡科を設置 |
| 昭和58年10月 |
南大洋生物資源研究室を設置 |
| 昭和59年 4月 |
組織改正により、底魚資源部(旧底魚海獣資源部)と海洋・南大洋部(旧海洋部)を設置 |
| 昭和63年 4月 |
全所的に組織を改編し、北洋資源第二研究室を廃止 |
| 昭和63年10月 |
外洋いか研究室を設置 |
| 平成 6年 6月 |
北洋資源部を再編整備し、生態系研究室を設置 |
| 平成 9年 4月 |
遠洋底魚研究室を廃止 |
| 平成10年10月 |
水産庁研究所の組織改正により、北洋資源研究部門を北海道区水産研究所に移転し、新たに 近海かつお・まぐろ資源部(かつお研究室・まぐろ研究室)、混獲生物研究室、数理解析研究室、国際資源管理研究官、国際海洋生物研究官を設置。
鯨類関連研究室を鯨類管理研究室と鯨類生態研究室に改編。
おっとせい研究室、まぐろ生態研究室、かつお・まぐろ調査研究室を廃止 |
| 平成13年 4月 |
水産庁の所属を離れ、独立行政法人水産総合研究センター遠洋水産研究所となる。
総務部、庶務課、会計課を廃止し、新たに総務課を設置。
国際資源管理研究官、国際海洋生物研究官を廃止し、新たに国際海洋資源研究官を設置 |
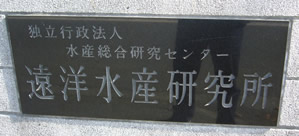 |
| 平成16年 4月 |
海洋・南大洋部を廃止し、企画連絡室に海洋研究グループを設置。
海洋研究グループに広域観測研究チームを設置。南大洋生物資源研究室を外洋資源部に移管 |
| 平成17年 4月 |
海洋研究グループを中央水産研究所内に移転。横浜駐在となる |
| 平成18年 3月 |
外洋資源部を中央水産研究所内に移転。横浜駐在となる |
| 平成18年 4月 |
組織改正により、総務課、企画連絡室を廃止し、新たに業務推進部を設置。
浮魚資源部を廃止し、熱帯性まぐろ資源部を設置。
近海かつお・まぐろ資源部を廃止し、温帯性まぐろ資源部を設置。
国際海洋資源研究官を廃止し、国際海洋資源研究員を設置。
|
| 平成19年11月 |
中央水産研究所に海洋データ解析センターを設置し、研究開発の効率化を進めるため海洋研究グループ及び広域観測研究チームを廃止。 |
| 平成21年 4月 |
組織改編により南大洋生物資源研究室を外洋生態系研究室へ改組 |
| 平成22年 4月 |
組織改編により温帯性まぐろ資源部をくろまぐろ資源部、熱帯性まぐろ資源部をかつお・まぐろ資源部へ改組
数理解析研究室を太平洋くろまぐろ資源研究室、生物特性研究室を太平洋くろまぐろ生物研究室へ改組 |
| 平成23年 4月 |
組織改編により、くろまぐろ資源部、かつお・まぐろ資源部、外洋資源部の研究室をグループへ改組。
くろまぐろ資源部の太平洋くろまぐろ資源研究室をくろまぐろ資源グループ、太平洋くろまぐろ生物研究室をくろまぐろ生物グループ、温帯性まぐろ研究室を温帯性まぐろグループへ改組。
かつお・まぐろ資源部のかつお・びんなが研究室をかつおグループ、熱帯性まぐろ研究室をまぐろ漁業資源グループ、混獲生物研究室を混獲生物グループへ改組、主幹研究員を設置。
外洋資源部の鯨類管理研究室と鯨類生態研究室を鯨類資源グループへ改組し主幹研究員を設置、外洋生態系研究室を外洋生態系グループ、外洋いか研究室を外洋いか資源グループへ改組。 |
| 平成23年9月 |
本年4月より第3期中期計画期間に入るにあたって、より一層の業務の重点化と効率化のために行った組織の一元化・再編に伴い、遠洋水産研究所の名称を国際水産資源研究所へと改正。 |
 |
| 平成25年4月 |
外洋資源部 外洋いか資源グループを東北区水産研究所資源海洋部に移管。 |
| 平成27年4月 |
法人名を独立行政法人から国立研究開発法人に改称。 |
| 平成28年4月 |
国立研究開発法人水産総合研究センターと独立行政法人水産大学校が統合し、国立研究開発法人水産研究・教育機構が発足しました。 |